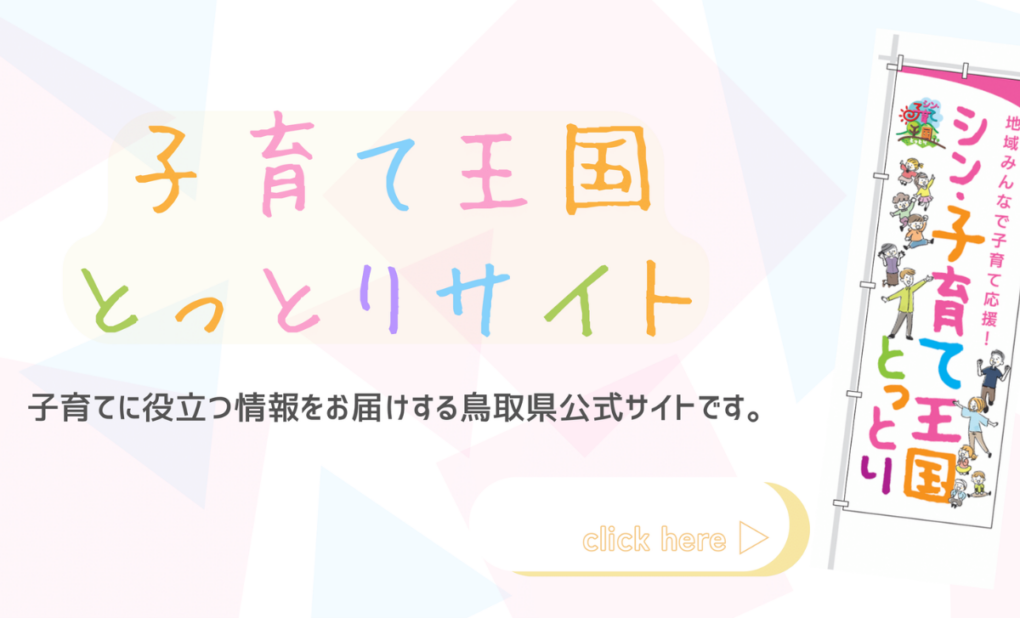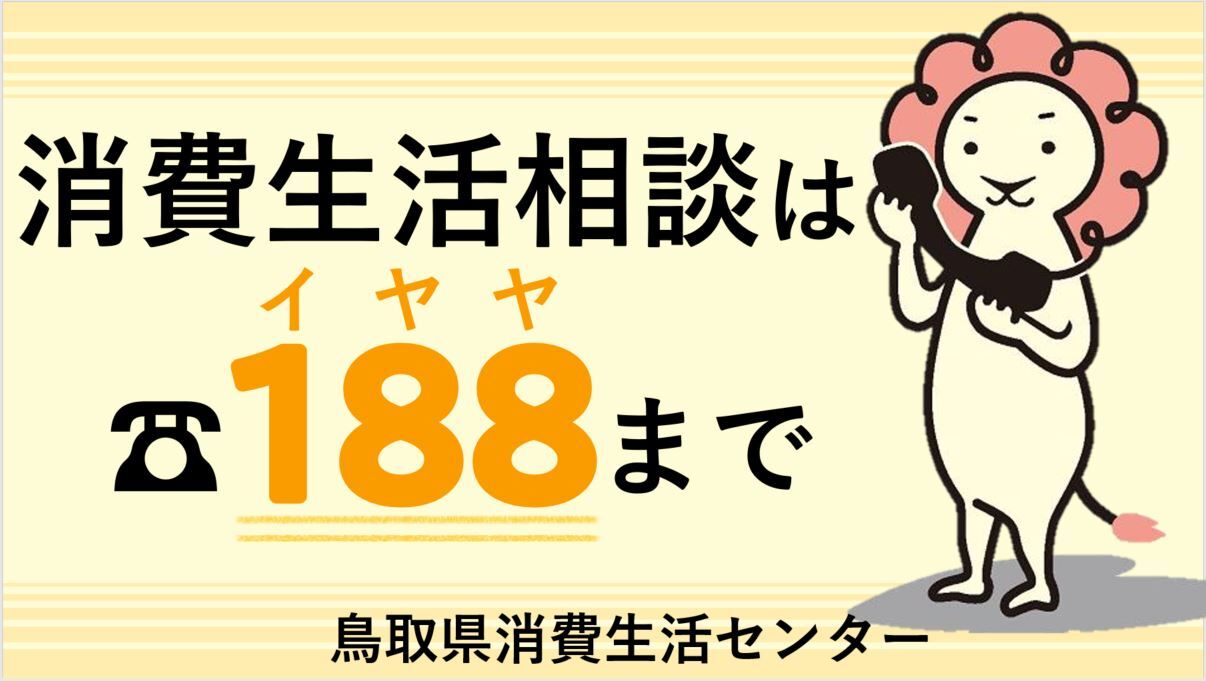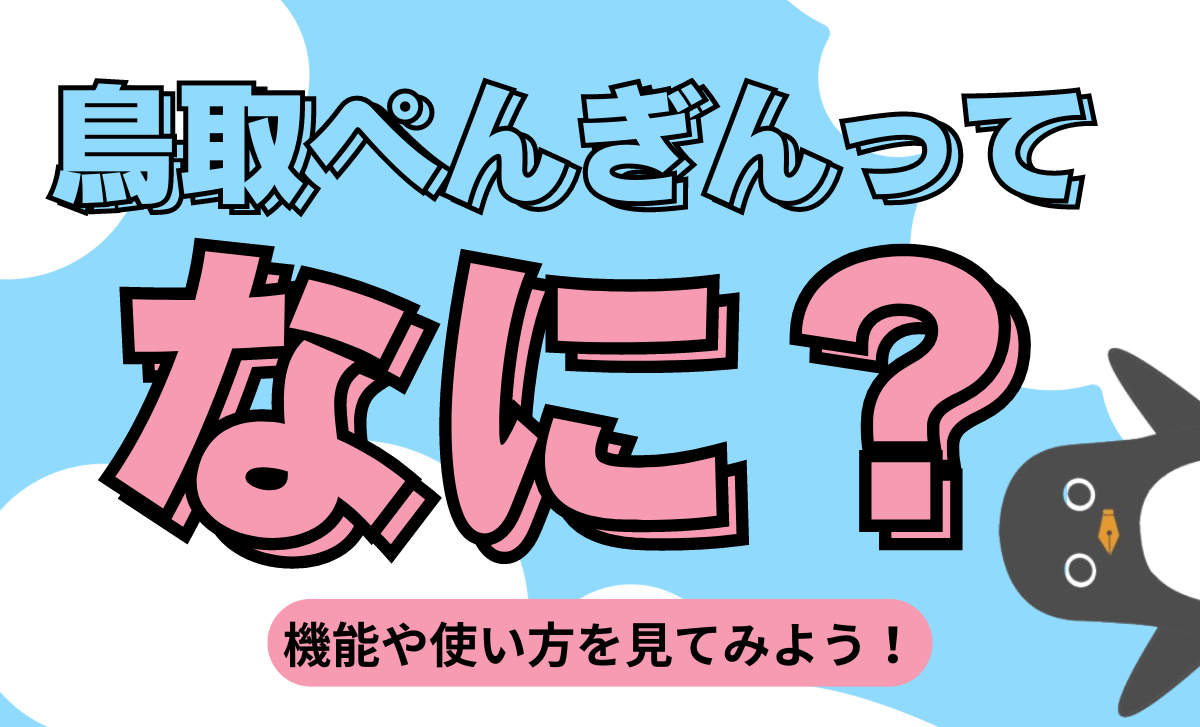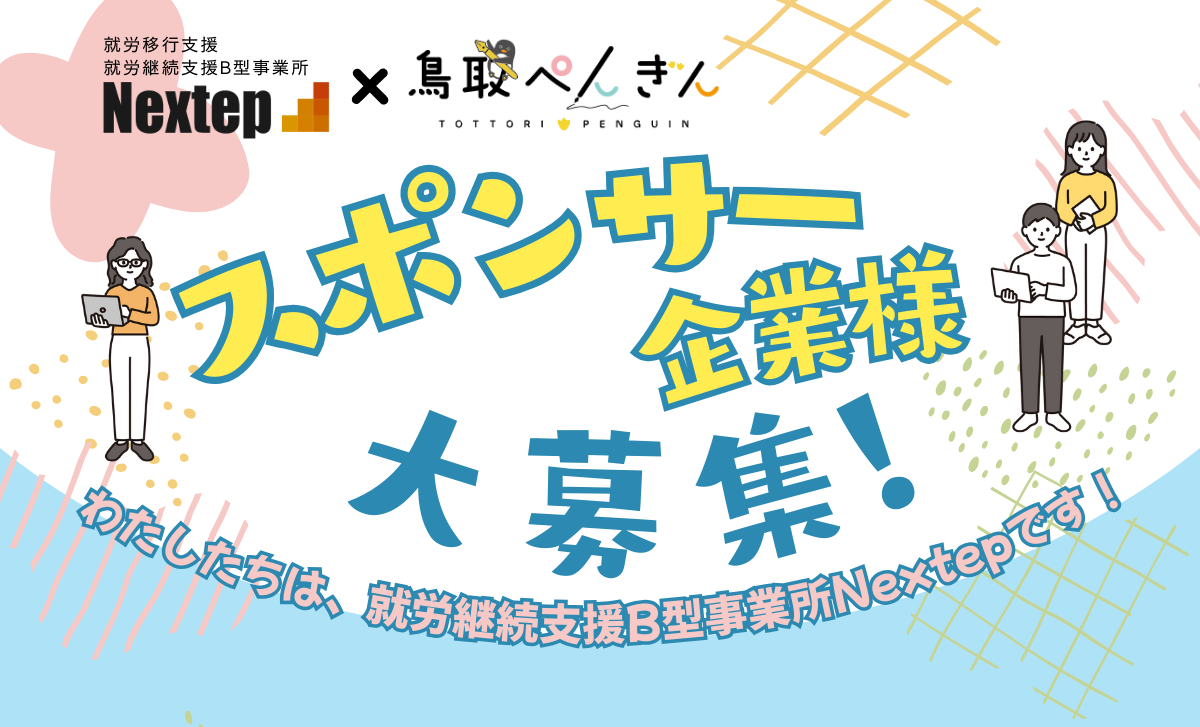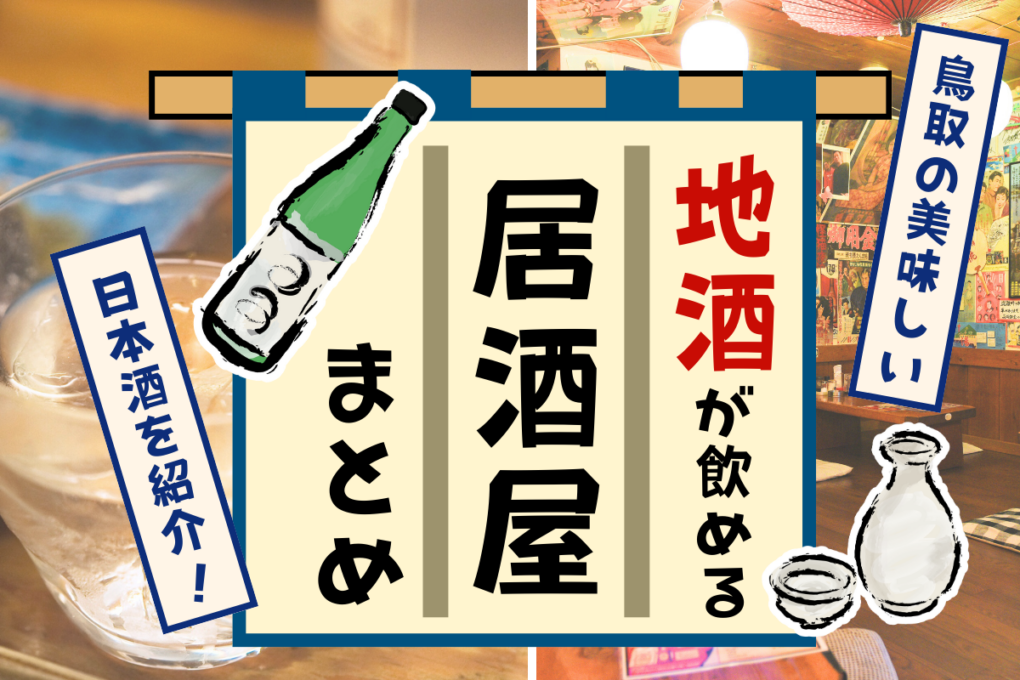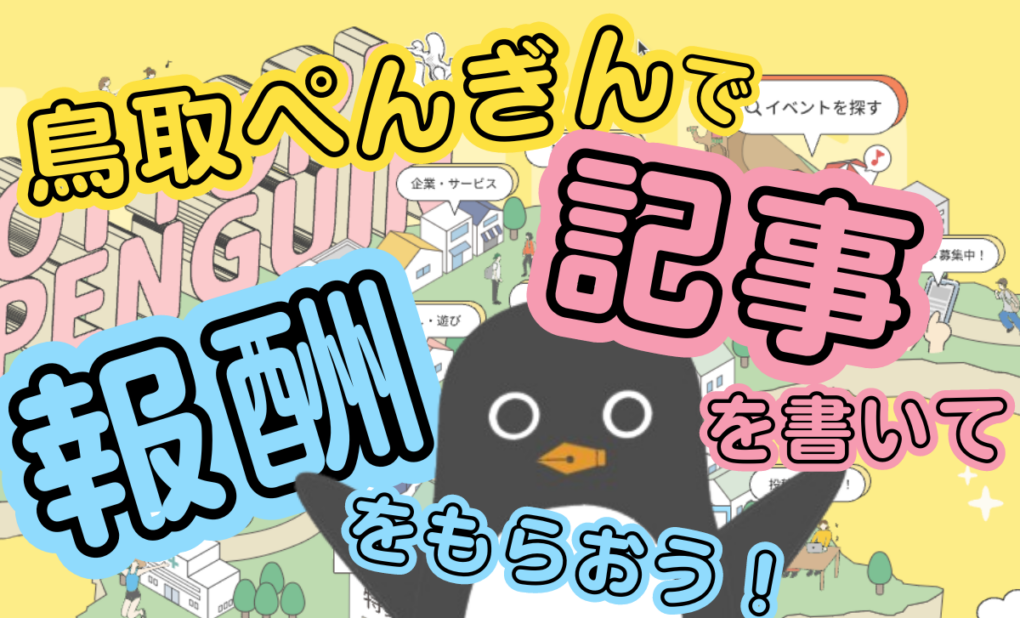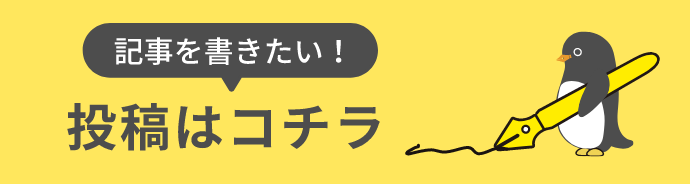Post記事
鳥取大学の学生がつなぐ「食」と「地域」ー 学生団体「すなめぐ」の挑戦
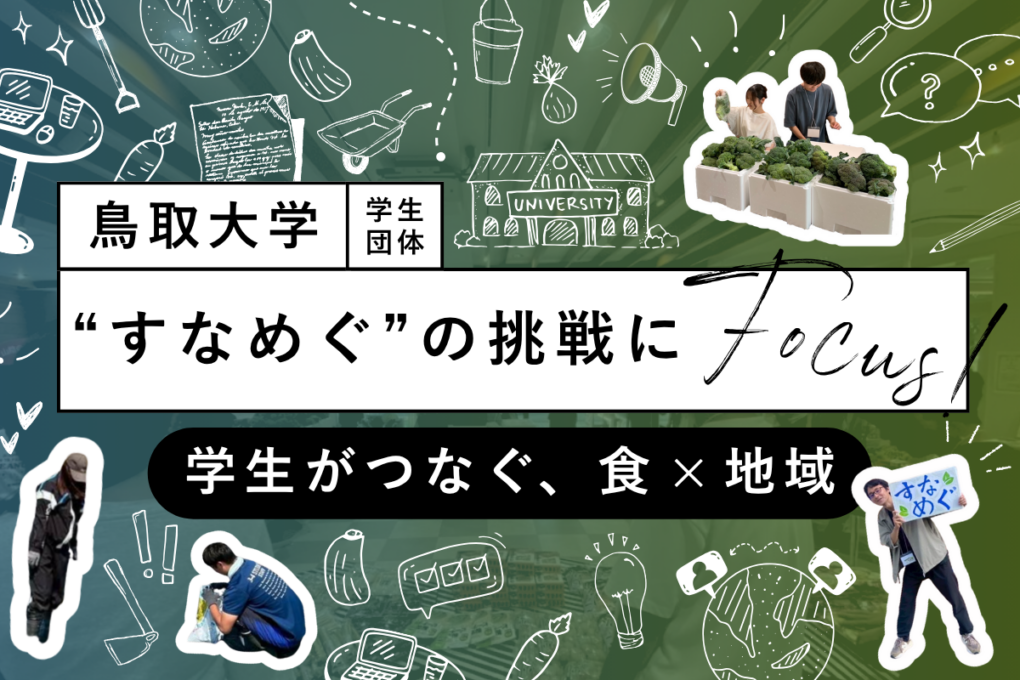
規格外や賞味期限が近いなどの理由で、まだ食べられるのに廃棄されてしまう食品。全国的に課題とされるフードロスの問題は、鳥取でも例外ではありません。
そんな課題に学生の立場から向き合おうとしているのが、鳥取大学の学生団体「すなめぐ」です。

「すなめぐ」は、規格外品などの食品を学生に届けたり、農業ボランティアを通じて農家と関わったりしながら、地域の暮らしを支えると同時に、地域とのつながりを生み出す“食の循環”を生み出そうとしています。
今回は、そんな「すなめぐ」代表の上原さんに、活動の背景やフードロス削減への思い、今後の展望についてインタビューした内容をお届けします!
目次
大学生を「食」で支える ― 学生団体「すなめぐ」とは?
「すなめぐ」について教えてください。
「すなめぐ」は2022年に活動をスタートした鳥取大学の学生団体です。学生支援とフードロス削減を目的に、食糧配付や農業ボランティアを行っています。
具体的にはどのような活動をしているのでしょうか?
2〜3ヶ月に一度、学生を対象にした無料の食糧配付を行っています。
具体的には、JAや「わったいな」さん、地元農家さんなどから譲り受けた規格外商品や、廃棄予定の食品を活用し、学生に無料で配付しています。そうすることで、学生の生活を支援すると同時に、フードロス削減にもつなげています。

学生さんへの無料食糧配付・・・!すばらしい活動ですね✨!定期的な配付イベントに向けての下準備も、みなさんでイチからされているんですか?
そうですね!週に1回ミーティングを開いて、企業や農家さんとのやり取りや進捗を確認しながら、食糧配付に向けて準備をしています。
企業さんのメール対応などは2年生が中心となり、それぞれ担当企業を持って役割を分担してくれていて、そのほかのメンバーは、イベントごとにスタッフとして活動しています。
僕自身は、外部とのやり取りに加え、会議の司会や団体の方向性を考える役割も担っています。


食糧配付以外にも始めた取り組みがあると聞きましたが。
昨年あたりから、地元の農家さんのところでお手伝いをする「農業ボランティア」を始めました。
食糧配付に加えて、農業ボランティアも始められたんですね!どんな経緯があったんですか?
きっかけは、活動メンバーが増えたこと、ですね。食糧配付は上級生が企業や団体とのやり取りを担当するので、1年生が関わる場面が少なくなってしまっていて。
なるほど。そこで“もっと参加できる活動を”と考えたんですね・・・!
「みんながもっと参加できる活動を増やしたい」という先輩からの提案もあり、農業ボランティアを始めることになりました。
最初はただのお手伝いのつもりだったんですが、農家さんから『学生のためなら配ってほしい』と野菜やお米をいただくこともあって。自然とつながりが生まれていきました。


そうして農家さんと直接関わっていくなかで、『ただ食品をもらって配るのではなく、作る大変さを理解した上で配ることに、大きな意味がある』という言葉をいただいたことがありました。
その言葉を通じて、私たち自身も当初想定していた以上に、この活動の意義を深く認識するようになりました。
「すなめぐ」との出会い
上原さんが「すなめぐ」に興味を持ったきっかけを教えてください。
実は私の専攻は化学・バイオ系で、「すなめぐ」の活動内容とは直接関係がありません(笑)
入学が決まったときにSNSでサークルを調べていて「すなめぐ」を知り、もともと興味のあったボランティアに挑戦してみたいと思ったのがきっかけです。
もう一つ、企業と繋がったり会議を行ったりと、ただの学生サークルにはない活動内容にも惹かれました。自分の意見が形になり、人の役に立ちながら行動で変化を起こせる。そんな点がとても魅力的で、「すなめぐならではの楽しさがある」のではと感じました。
なるほど、サークルでありボランティアであり、さらにビジネスっぽい要素もある・・・ 学生生活の中で、なかなか味わえない経験ですよね!

実際に活動してみて印象に残っていることは?
活動をしていて印象に残っていることを教えてください。
やっぱり一番は、企業さんに連絡を取ってメールの文章を考えたり、今回のような取材を受けたりする時ですね。自分でも想像してなかったことをやっているなと不思議に思うほどです。
社会人とのやり取り、はじめは緊張しますよね・・・!
緊張しました!今までは、教授への連絡くらいしか経験がなかったので(笑)
社会人向けのメールを書くのは初めてで、とても貴重な経験ができています。
また、鳥取市の異業種交流団体『とりもぶ』の集まりに参加したときは、名刺交換や人前での挨拶など、普段の学生生活ではできない経験をさせてもらいました。初めてのことばかりで緊張しましたが、とても新鮮で楽しかったですね。
「すなめぐ」の変化と課題
団体に入った頃と現在で変化したことや違いはありますか?
僕が入った当初は、ちょうど創設メンバーが抜けた直後で、活動が少し不安定な時期でした。やらなければいけないことが多く、手一杯な感じでしたね。それもあって、世代間のつながりも薄かったように感じます。
でも今は、だいぶ雰囲気が変わりました。以前よりもつながりが濃く、深くなってきていると感じます。
以前よりも世代間のつながりが深くなっているんですね!その要因は何だと思いますか?
大きな要因といえるのは「引き継ぎ」ですね。僕たちが2年生になったら、上の世代から活動を引き継がなければならない。仲良くなっていないとスムーズに進められない、という危機感があったんです。
そこで、意識的に交流を増やすようにしました。活動の悩みを話し合ったり、先輩に相談したり。そうやって自然と集まる場を作る中で、主体的に関係を深めるようになりました。
結果として、以前よりもしっかりとしたつながりを築けていると思います。
結果として、以前よりもしっかりとしたつながりを築けていると思います!
団体を運営していく中での課題
最近は、会議でみんなが意見を出しやすいよう、話しやすい雰囲気作りを意識していますが、やはり難しさを感じることがありますね。

創設者がもういない今、立ち上げ当初ほどの熱量はどうしても薄れてしまっている気がします。
新しく入ってくるメンバーも、「こういうことができるのだろう」と期待しながら参加している状況で、僕はそこに、何か経験や刺激を与えていかないといけない立場。でも、どんなことを求められているのか、まだ掴み切れていないのが正直な悩みです。
結局は、メンバーそれぞれが何を考えていて、どんな思いを持っているのか。それをどう汲み上げ、この団体に活かしていけるのか。そこが今一番の課題だと思っています。
一人ひとりの思いを大事にしながら運営していこうとする姿勢、本当に素晴らしいですね! その姿勢があるからこそ、団体としての成長につながっているのだと感じます。
今後について
今後、どのような団体にしていきたいですか。
とりあえず一番の目標は、“「すなめぐ」という団体を、長く続けられるカタチにする”ことです。

今はまだ手探りの状態で、会議の進め方ひとつとっても、本当はもっと効率的なやり方があるはずなんですけど、学生だけで運営しているので、顧問の先生のように『こうした方がいいよ』と指導してくれる人がいないんですよね。
活動が止まってしまったり、意見が出にくくなったりしたときも、修正できるのは学生だけ。だからこそ、意見が埋もれないように、少しでも話しやすい雰囲気を作ることが必要だと思っています。
ボランティア団体って、自分たちが『やろう』と思わないと何も進まないんです。待っているだけでは状況は変わらない。だからまずはこちらから働きかけて、一度活動に参加してもらい、その経験を持ち帰って考えてもらう。その繰り返しで初めて理解が深まっていくんじゃないかと思います。
“待つのではなく、自分たちから動く”という姿勢、とても素晴らしいですね・・・!
今年に入ってからも、どう団体を盛り上げていくか話し合いました。その中で出た結論は、メンバーのモチベーションをどう維持・向上させるかが大事だということ。
例えば賞状がもらえるコンテストに応募してみたり、とにかく一歩行動してみること。異業種交流団体「とりもぶ」さんに参加して協力先を探すなど、団体を外に広げていく試みも始めています。
行動してみないと見えてこないものがある。そうした経験を重ねながら、「すなめぐ」を次の世代にもつなげていける団体にしていきたいと思っています!
次回イベント
次回開催予定の食糧配付イベントについて、ぜひ教えてください。

10月24日(金)に鳥取大学内で食糧配付の開催を予定しています。
今、まさに絶賛準備中ですので、ぜひ学生のみなさん、楽しみにしていてください!
詳細が決まり次第、SNS等で告知しますので、ぜひチェックお願いします!

| 「すなめぐ」お問合わせ先 |
|---|
| sakyuumegumi@gmail.com |
取材後記
「待っているだけでは活動は進まない。まずは自分たちから動いて、経験してもらうことが大切だと思うんです。」
そう話す上原さんの言葉からは、学生でありながら運営を担う責任感と前向きなエネルギーが伝わってきました。
学生支援やフードロス削減といった目的の先には、地域の人々や企業との新しいつながりが広がっています。
「すなめぐ」の挑戦は、これからも続いていきます。